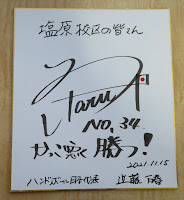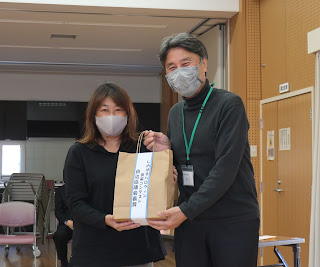塩原校区は、11月21日の日曜日午前9時から自主防災会主催の「総合防災訓練」を開催しました。
今年はコロナ感染予防の観点から、地域住民が一堂に集まり小学校まで避難する従来の方式を避け、防災委員や各町の役員による訓練を行いました。
「地域の人が集まって避難する訓練」から「避難者を受け入れる側の訓練」――となりました。
訓練は2部制。
1部は洪水、地震による危険個所点検と災害弱者宅の訪問。
2部は公民館に集まり、令和元年に作成した避難所運営マニュアルの補強「避難者による避難所運営」の勉強会を行いました。
■
1部 「危険個所点検と災害弱者訪問」 ■
 |
| 塩原東公園(塩原4丁目1区・2区)の様子 |
 |
| 塩原公園(塩原1丁目2区)の様子 |
 |
| 塩原西公園(塩原3丁目1区・2区・3区)の様子 |
◇危険個所点検◇
・「消防署が見に来るぐらい川より低い所や消防車が入れない狭い道路がある」
・「団地で建物はしっかりしているが、地下の駐車場は浸水する可能性がある」
・「道路が低く浸水の可能性があり避難経路に使えない」
・コンクリート塀が高い所があり、地震では避難経路には使えない。
・高い樹木が電線と絡まっている箇所があり、強風で停電する心配がある。
・公園に高さ4mの記念碑があり危険。行政に対策をお願いしたい。
・補強が無い墓地があり、改善の余地がある。
・空き家があり、自治会から対処を申し入れたが放置されている。行政からの働きかけをお願いしたい。
・団地にはエレベーターが多く、地震による停電で使えなくなる可能性がある。
・団地の1階に機械室があり、洪水では断水が予想される。
・道路に電線が多く、断線や電柱倒壊の危険がある。
◇災害時弱者訪問◇
・要支援者は14名。民生委員と独り暮らし人を重点に7名を訪問。お互いに連絡をし合うよう話しあった。
・住民票があり、要支援者の名簿が届いたが本人は居ない。どうしたらいいのか?
・要支援者5名のうち4名は1階が住居。ハザードマップでは40cm~50cmの浸水予想。早めの避難を伝えた。
・要支援者15世帯のうち7世帯を自治会と老人会で訪問した。2世帯は留守だった。
・要支援者は20名。全部回ることはできなかった。
◇その他◇
・電気、水道、トイレ完備のいこいの家(避難所)があるが、緊急時の防災グッズがない。最低限の用具を準備してもらいたい。
・自治会で独自のハザードマップを作成。自宅の浸水がわかるようにしたチラシを配布した。
・幼稚園の横に1.8mぐらいの塀があり危険。
■
2部 「勉強会・避難者による避難所運営」 ■
塩原校区は令和元年に「避難所運営マニュアル」を作成したが、時間との兼ね合いもあり、地域住民が一時避難場所に集まり小学校へ避難し、受け入れるための避難所を開設するまでの内容となっていた。
今回の訓練では避難者を受け入れ、避難所を如何に運営するか――「避難者による避難所運営」を考える勉強会とした。
◇避難所運営の方針◇
骨子は①避難所の運営は避難して来た人が運営することを基本とする。
②自治協議会の各種団体に「運営班」を設け、避難者と協働して運営する。
③「運営班」は平時に作業内容を研究、習得して避難所では先生役を担ってもらう。
――というものです。
◇各班の役割り◇
平時に何をすればいいのか?災害発生時の役割りはどういうことがあるのか?
これまでの事例を参考に考えてみました。内容は多岐にわたります。避難所運営に必要な資機材、知識――どれを採っても難しさが立ちはだかります。
塩原校区は避難所運営の実体験に学びながら一つでも二つでも実現することを目標に今後の取り組みを進めていきたいと思っています。
文章 川添繁美